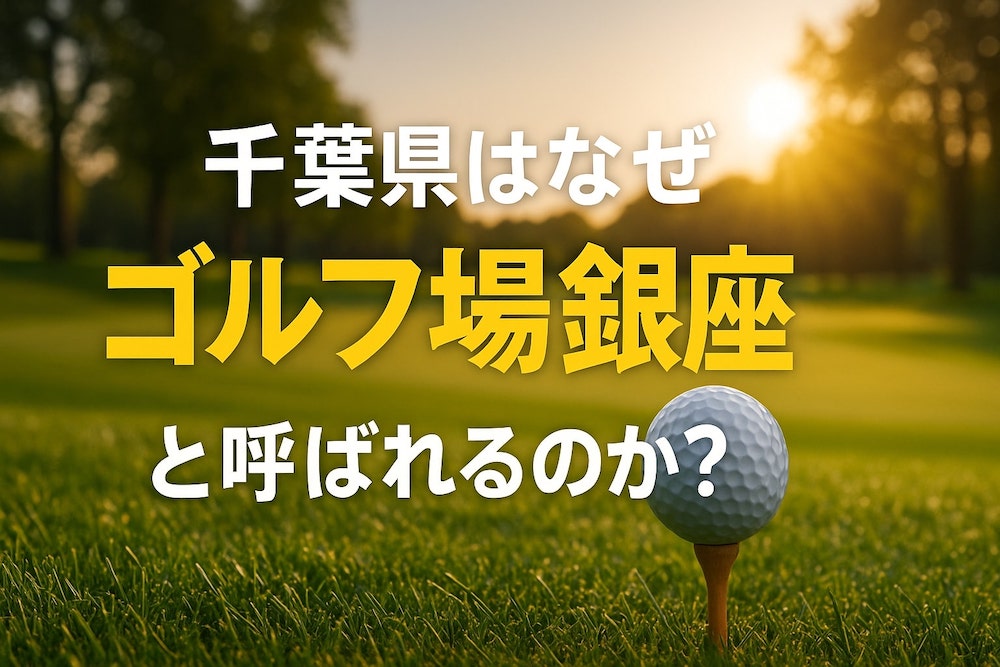「ゴルフ場銀座」—この言葉を聞いたことがあるだろうか。
銀座という言葉は、何かが多く集まる場所を比喩的に表現する際に使われる。
そして千葉県は、まさにゴルフ場が集中する「銀座」なのだ。
私は千葉県市原市で生まれ育ち、幼い頃からフェアウェイの緑が日常風景だった。
35年以上にわたりゴルフ業界に身を置き、バブル期には全国の新設コースを飛び回ってきた。
そんな私の視点から、千葉県が「ゴルフ場銀座」と呼ばれる理由を、歴史・地理・産業の三位一体で読み解いていきたい。
千葉県のゴルフ場密集の実態
ゴルフ場数と全国的な位置づけ
千葉県は全国2位(最新の統計では1位とも)となる約160のゴルフ場を有している。
この数字だけを見ても、いかに千葉県にゴルフ場が集中しているかがわかるだろう。
特に全国の約1700ある市町村の中で、最もゴルフ場が多いのが千葉県の市原市だ。
市原市には32クラブ33カ所ものゴルフ場があり、市の面積の約11%をゴルフ場が占めている。
これは国内の自治体で最多の数字だ。
まさに「ゴルフ場銀座」の中心地といえる。
市原・長柄・茂原エリアに見る密度の高さ
私が編集者として全国のコースを巡った経験から言うと、千葉県中央部の市原・長柄・茂原のエリアは特別な場所だ。
丘を一つ越えれば、また別のゴルフ場が現れる。
道路沿いには「ゴルフ場案内」の看板が連なり、朝夕にはゴルフバッグを持った人々で駅前が賑わう。
このエリアでは、ゴルフ場の敷地が隣接していることも珍しくない。
あるホールのティーグラウンドから、隣のコースのグリーンが見えることもある。
これほどゴルフ場が密集している地域は、全国でもここだけだろう。
他県との比較:なぜ千葉に集中したのか
ゴルフ場の数では北海道や兵庫県も上位に名を連ねるが、人口密度や面積比で見ると、千葉県の集中度は突出している。
例えば栃木県は人口1万人あたりのゴルフ場数が0.92と高いが、千葉県は人口が多いにも関わらず0.26と高い数値を示している。
それでは、なぜここまで千葉県にゴルフ場が集中したのか?
それを理解するには、バブル期の開発状況や地理的特性を紐解く必要がある。
“ゴルフ場銀座”が生まれた理由
バブル期の開発ラッシュと用地事情
1980年代後半から90年代初頭のバブル経済期、全国でゴルフ場開発が急増した。
「会員権」というキーワードが飛び交い、ステータスの象徴としてゴルフが爆発的に人気を集めた時代だ。
私が編集者時代にバブル期のゴルフ場開発を取材していた頃、千葉県ではほぼ毎月のように新しいコースがオープンしていた。
当時の開発事情を知る業界人によれば、千葉県には以下の優位性があったという。
- 土地価格の相対的な安さ
- 既存の農地や山林の転用のしやすさ
- 地方自治体の開発への理解
「千葉県は東京からのアクセスがよく、土地価格も手頃で、自治体も協力的だった。ゴルフ場開発にとっては三拍子揃った最適地だった」(あるゴルフ場設計者)
東京圏からのアクセスの良さ
千葉県、特に市原市周辺は東京都心から車で1時間程度という好立地にある。
京葉道路や東京湾アクアラインの開通により、アクセスはさらに向上した。
首都圏のビジネスパーソンにとって、日帰りゴルフの理想的な距離だったのだ。
鉄道網も発達しており、駅からクラブバスを運行するゴルフ場も多い。
車を持たないゴルファーにとっても便利な環境が整っていた。
この「日帰りしやすさ」こそが、千葉県最大の強みだったと言える。
地形・気候がもたらすコース設計の自由度
私はゴルフ場開発の取材を通じて、多くの設計者と意見を交わしてきた。
彼らが口を揃えて言うのは、千葉県の地形と気候の素晴らしさだ。
千葉県の地形的特徴:
- 北部は関東平野の一部で平坦
- 中央から南部にかけては適度な起伏を持つ丘陵地
- 極端な高低差がなく設計しやすい
気候的特徴:
- 三方を海に囲まれた海洋性の温暖な気候
- 冬暖かく夏涼しい
- 黒潮の影響で年間を通してゴルフに適した環境
「千葉県は高い山がなく比較的平坦な地形で、冬暖かく夏涼しい海洋性の温暖な気候のためゴルフプレーに適している」というのは、多くのゴルフガイドで紹介される千葉県の特徴だ。
地元住民とゴルフの共生
「日常にフェアウェイ」—育まれた地域文化
私が子供の頃の市原市では、ゴルフ場は特別な場所ではなく、日常風景の一部だった。
地元の子供たちはコース脇の林でカブトムシを捕り、休日になるとキャディのアルバイトに精を出す。
学校の遠足でコースを横切るショートカットをすることもあった。
高校の同級生の多くは、就職先としてゴルフ場を選んだ。
グリーンキーパー、レストランスタッフ、フロント業務など、様々な職種がある。
地元の県立市原高校の園芸科には「緑地管理コース」があり、芝生管理の専門教育も行われている。
ゴルフ場と雇用・経済のつながり
市原市の統計によれば、市内のゴルフ場で働く人口は約2100人。
関連施設での雇用も含めると、かなりの雇用を創出している。
年間約160万人のゴルファーが訪れ、観光客の半数近くを占めるという。
ゴルフ場利用税は市原市に年間約6.4億円の歳入をもたらしている。
これは市の重要な財源となっており、地域経済への貢献は計り知れない。
「ゴルフ場がなければ、この地域の経済は成り立たない」というのは、決して大げさな表現ではない。
市原市は「ゴルフの街いちはら」を掲げ、以下の取り組みを行っている:
- いちはらゴルフ場巡り33(33カ所のゴルフ場を巡るスタンプラリー)
- 手ぶらdeゴルフ(初心者向け体験プログラム)
- ふるさと納税の返礼品としてのゴルフ場プレー券
- PGAとの連携協定によるジュニアゴルファー育成
住民目線の景観と自然とのバランス
ゴルフ場は自然環境への影響が懸念されることもあるが、千葉県では比較的調和がとれている。
これは千葉県が「ゴルフ場等の開発事業に関する指導要綱」を定め、環境保全に配慮してきた結果だ。
開発区域内には原則として50%以上の森林を確保することや、周辺部に30メートル以上の森林帯を設けることなどが定められている。
こうした規制により、ゴルフ場と周辺環境との調和が保たれているのだ。
地元住民にとっては、ゴルフ場の緑地は貴重な自然空間となっている。
「ゴルフ場の緑がなければ、この地域はもっと開発され、コンクリートだらけになっていたかもしれない」という声も聞かれる。
コース設計とメンテナンスの視点から見る千葉
設計家が好む千葉の特性とは
私はゴルフコース設計の取材を通じて、多くの設計家と交流してきた。
彼らが千葉県を好む理由は主に以下の3点に集約される。
1. 多様な地形を活かせる自由度
千葉県の丘陵地は、フラットな北部から起伏に富む中南部まで、様々な表情を持つ。
設計家の意図を実現しやすい地形が広がっている。
2. 年間を通じた芝の生育環境の良さ
温暖な気候は、日本芝と西洋芝の両方の生育に適している。
メンテナンス面でも管理しやすい環境だ。
3. 排水性の良い土壌
関東ローム層を基盤とする千葉の土壌は排水性に優れている。
これはコース管理において大きな利点となる。
名門コースの育て方と維持技術
1931年開場の我孫子ゴルフ倶楽部や1932年開場の鷹之台カンツリー倶楽部など、千葉県には長い歴史を持つ名門コースが数多く存在する。
これらのコースがどのように維持されてきたのか、その秘密に迫りたい。
「千葉の名門コースは、伝統を守りながらも時代に合わせた革新を怠らない。それが長く愛される理由だ」(某名門コースのコース管理責任者)
名門コースの多くは、C・H・アリソンの影響を受けた井上誠一や上田治など、日本を代表する設計家の手によるものだ。
彼らの設計思想が、今も千葉県のコースに息づいている。
近年は外国人設計家の作品も増えており、ピート・ダイ設計の成田ヒルズカントリークラブなど、国際的な設計思想を取り入れたコースも人気を集めている。
“通好み”が語る、千葉の芝と風土
長年千葉のコースを渡り歩いてきた常連ゴルファーたちは、その魅力をどう語るだろうか。
私が取材した「通」たちの言葉を紹介しよう。
千葉コースの芝の特徴:
- 北部:関東ローム層の赤土が基盤となり、弾力のある打感
- 中部:マサ土と粘土の混合土壌で、絶妙なグリーンスピード
- 南部:黒潮の影響による温暖な気候で、冬でも良好なコンディション
「千葉のコースはグリーンの状態がいい。特に秋のベントグリーンは絶品だ」と語るのは、月に10ラウンドする常連客だ。
確かに秋の千葉のコースは、最高のコンディションを誇る。
千葉のゴルフ場が充実している一方で、通好みのゴルファーたちは時に埼玉方面のコースにも足を運ぶ。
特に戦略性の高さで評判のオリムピックナショナルGC WESTの口コミを参考にするプレイヤーも増えている。
丁寧なコース管理と造形美から学ぶべき点は多く、千葉のゴルフ場設計にも影響を与えている部分があるだろう。
千葉の”ゴルフ場銀座”は今
ポストバブルの淘汰と再編
バブル崩壊後、ゴルフ業界は厳しい時代を迎えた。
多くのゴルフ場が経営難に陥り、倒産や経営権の移転が相次いだ。
千葉県も例外ではなく、一部のゴルフ場は姿を消していった。
しかし、淘汰と再編を経て、生き残ったゴルフ場は強さを増している。
大手ゴルフ場運営会社による集約化が進み、経営の効率化が図られた。
また、メンバーシップ制からパブリック化へとビジネスモデルを転換するコースも増えている。
サステナブル経営と地域連携の試み
現在の千葉県のゴルフ場は、持続可能な経営を模索している。
環境に配慮した農薬の使用削減や、水資源の有効活用などの取り組みも進んでいる。
市原市では、ゴルフ場とクラブハウスのレストランを一般に開放する取り組みも始まっている。
飲食店が少ない地域の人々に喜ばれると同時に、ゴルフ場の新たな収入源となっている。
また、市原市とPGAは「ゴルフの街いちはら」の推進に向けた連携協定を締結。
ジュニアゴルファーの育成や地域活性化に取り組んでいる。
市原高校の園芸科とゴルフ場の連携により、グリーンキーパーなどの人材育成も行われている。
“贅沢な社交”から”心の余白”へ—ゴルフの再定義
バブル期、ゴルフは「贅沢な社交場」としての側面が強調されていた。
しかし今、ゴルフは「心の余白」を提供する場所として再定義されつつある。
コロナ禍を経て、屋外でソーシャルディスタンスを保ちながら楽しめるスポーツとして再評価された。
若い世代や女性プレーヤーも増加傾向にあり、ゴルフ人口の裾野は広がっている。
千葉の「ゴルフ場銀座」も、こうした時代の変化に対応している。
アーリーモーニングや薄暮プレーなど、多様なライフスタイルに合わせたサービスを提供。
ゴルフ場は「特別な場所」から「日常に寄り添う場所」へと進化を遂げている。
まとめ
千葉県が「ゴルフ場銀座」と呼ばれる理由は、単にゴルフ場の数が多いというだけではない。
バブル期の開発ラッシュ、東京からの好アクセス、ゴルフに適した地形と気候、そして何より地域と共生してきた歴史が、この称号をもたらしたのだ。
地元出身の私が見てきた千葉のゴルフ場は、時代と共に変化しながらも、常に地域に根ざしてきた。
ゴルフ場と地域が互いに支え合い、Win-Winの関係を構築してきた実例といえる。
これからの千葉のゴルフ場はどう変わっていくのか。
市原市が目指す「ゴルフの聖地」は実現するのか。
時代の変化に対応しながら、千葉の「ゴルフ場銀座」は新たな価値を生み出し続けるだろう。
そして我々ゴルファーは、その恩恵を受けながら、千葉の豊かな自然の中でプレーを楽しむことができる。
千葉の地に根ざす「ゴルフのある風景」を、次世代へと繋げていきたい。
最終更新日 2025年5月13日 by plavacek